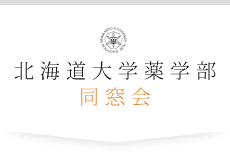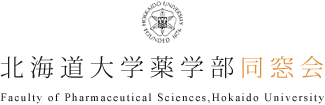お知らせ
【研究最前線】医療現場から引き継いだ医療薬学・臨床薬学研究/井関 健(22期・臨床薬学教育研究センター 招聘教授)
2025.01.20
定年退職して5年近くも経過した今になって、研究のまとめを寄稿してくれという依頼が「芳香」から届き、若干困惑しているが、少し自分史の思い出話をして良いなら、という条件で執筆させていただくことにした。しばしの間、むかし話に付き合っていただければ嬉しい限りである。
私の社会人としての活動は、北海道大学薬学部を昭和54年に卒業後、大学院修士課程を中途退学して昭和56年夏から北海道大学医学部附属病院薬剤部に於いて薬剤師としてスタートした。薬剤師であるから研究業務はその職務には含まれない、あくまでも就労時間が終わってからの自主活動である。今でも時々言われることではあるが、薬剤師として仕事をするなら研究は必要ない、研究したいなら薬剤師にはなるな、という雰囲気はかつてはもっとひどいもので、大学院を途中退学して病院薬剤師になった私を取り巻く環境は研究とは無縁の世界であるように思えた。
ましてや現在と違って「臨床研究」というドライサイエンスの分野も薬学では確立されていなかったし、研究といえばウェットな実験研究であったから、同級生を始め私を知る人間は、皆「これで井関は研究をやめた!」と思ったとしても不思議ではない。
しかし、私にとって幸いであったのは勤務した病院が大学附属病院であったということである。大学病院というところは、まだ確立していない治療方法、医薬品候補を実際に医療に使用して、その是非を評価していくことをその責務の一つにしている。すなわち、大学病院は、リスクのある医療を実施し、その安全性と有効性を明らかにすることによって、一般の市中病院やクリニックにおける標準医療を前進させる、という役割を担っている。このことは、未知の現象を明らかにし、そのメカニズムを検証するという「研究」と非常に共通する部分がある。
従って、大学病院においては、診療・教育・研究が三位一体となって実践されてきた。そのため、薬剤師も研究を行う土壌があったと言える。もっとも、私が北海道大学医学部附属病院に就職した時には、医師は診療・研究・教育をバランスよく実行しているのに、薬剤師は業務・業務・業務と強調されるのは何故なのかなと疑問に思ったのも事実である。(一部抜粋)
全文は同窓会HPの「芳香SCIENCE」から閲覧できます。