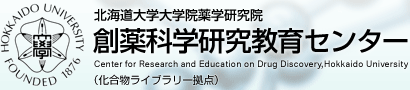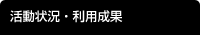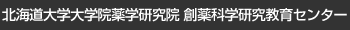創薬ネットワークセミナーが開催されました
創薬ネットワークセミナー 有効な治療法のない患者さんへ薬を届けるために

日時:
2013年10月17日(木) 17:00~19:00
会場:
北海道大学 医学部 臨床大講堂( 札幌市北区北15条西7丁目)
プログラム:
17:00~17:05 未来創薬・医療イノベーション拠点形成の紹介
高山 大( 未来創薬・医療イノベーション推進室 室長 特任教授)
17:05~17:10 創薬科学研究教育センターの紹介
前仲 勝実(大学院薬学研究院創薬科学研究教育センター センター長 教授)
17:10~18:05 座長/佐藤 典宏( 高度先進医療支援センター センター長 教授)
「稀少疾患:特発性肺線維症の創薬、臨床試験と実臨床への導入」
吾妻 安良太 先生 日本医科大学 呼吸器内科 教授
18:05~19:00 座長/前仲 勝実( 大学院薬学研究院創薬科学研究教育センター センター長 教授)
「呼吸器感染症ウイルスの病原性発現理解が拓くワクチン開発と創薬への道」
竹田 誠 先生 国立感染症研究所 ウイルス第三部 部長
【開催趣旨】
科学の発達した今日においてもなお、治療法の確立されていない疾患は数多く存在し、新たな治療法、治療薬の 開発が待ち望まれている。それらの医療ニーズ(アンメットメデイカルニーズ)を発掘することは治療法や医薬品 の開発にとって最も重要なことであるが、治療法の開発に取り組む大学研究室や製薬企業には医療現場でのア ンメットメディカルニーズが必ずしも十分に伝えられておらず、一方、医療従事者にはアンメットメディカルニーズ を治療薬開発に結び付ける方法論や技術が良く理解されていないのが現状である。 本セミナーはこのようなギャップの解消を目指した活動の一環として実施するものであり、アカデミアとして創薬 研究に携わっておられる著名研究者をお招きし、アンメットメディカルニーズを創薬シーズにつなげるための方 法論や技術の一端を紹介することで、アンメットメディカルニーズの発掘と治療法開発の一助としたい。
【主 催】
北海道大学 未来創薬・医療イノベーション拠点形成、創薬科学研究教育センター
【後 援】
北海道大学URA ステーション
【連絡先】
北海道大学病院 高度先進医療支援センター 創薬イノベーション支援室
TEL:011-706-7429 FAX:011-706-7977 E-mail:sayukohashiba@huhp.hokudai.ac.jp
担当 橋場 砂有子
北海道大学大学院薬学研究院 創薬科学研究教育センター
TEL:011-706-3773 FAX:011-706-4983
E-mail:rie-n@pharm.hokudai.ac.jp
担当 中井戸 梨恵
【講演1】 吾妻 安良太 先生(日本医科大学 呼吸器内科 教授)
稀少疾患:特発性肺線維症の創薬、臨床試験と実臨床への導入
特発性肺線維症(IPF)はunmet needs の治療薬に乏しい疾患として、これまで創薬が遅れていた。 近年、ピルフェニドンの市場導入を機に、IPF の臨床試験が国際的に活発となっている。 2000 年以前は小規模の単施設研究であったものが、現在では国際共同多施設の試験が企画さ れ、最新の分子標的薬を用いた有意差検定が行われている。しかし、治療効果が検証されたも のは少なく、背景にはIPF 病態の多様性、複雑性、難治性が指摘されている。評価指標の選定 を巡っても、意見が分かれるところである。ピルフェニドン臨床試験では肺活量(VC)の変化量 が主要評価項目とされ、他に無増悪生存期間、運動対応能が評価された。Nintedanib 第Ⅱ相 試験ではFVC 変化量と急性増悪を評価項目とした。あらかじめ設定する主要評価項目が理論に 基づく設定であるよりも、経験に基づく場合が多い。近年ではその多くがFVC を主要評価に用い ている。6 分間歩行試験も運動対応能力を反映するが、試験によってまちまちなのが実情である。 生存(os)が究極の評価指標であるとしても、臨床試験が薬価の高騰を誘導することは明白である。 医学的検証が経済の傘の下で議論される問題がある。 検証されたEBM をいかに個別の患者に届けるのか。また有意差のなかった治療を施すのは 無意味なのか。稀少疾患に対する現代医療のあり方を考えたい。
【講演 2】 竹田 誠 先生(国立感染症研究所 ウイルス第三部 部長)
呼吸器感染症ウイルスの病原性発現理解が拓くワクチン開発と創薬への道
経気道的に感染するウイルスは、一旦流行が始まるとその急速な拡大を阻止することは非常に 困難である。新興感染症の場合には、その脅威はさらに大きい。ワクチン開発に加え、治療薬 の開発が強く期待される。近年でもH7N9 インフルエンザ、MERS コロナウイルスなど、現実的 な脅威が続いている。麻疹ウイルスは、もっとも伝染力の強い病原体であり、世界中の都市で感 染しうるウイルスとしては最も致死率が高い病原体である。ワクチンを用いた世界的な排除が目 標にされている。イヌジステンパーウイルス(CDV)は、いわば犬の麻疹と言える疾病であるが、 近年、サルに対して致死性の大流行を起こしており、ヒトへの脅威となる可能性が報告されている。 本講演では、これら呼吸器感染症ウイルスと、宿主プロテアーゼや受容体との相互作用の解明を 通じて、新たなワクチン開発や創薬への可能性について発表する。